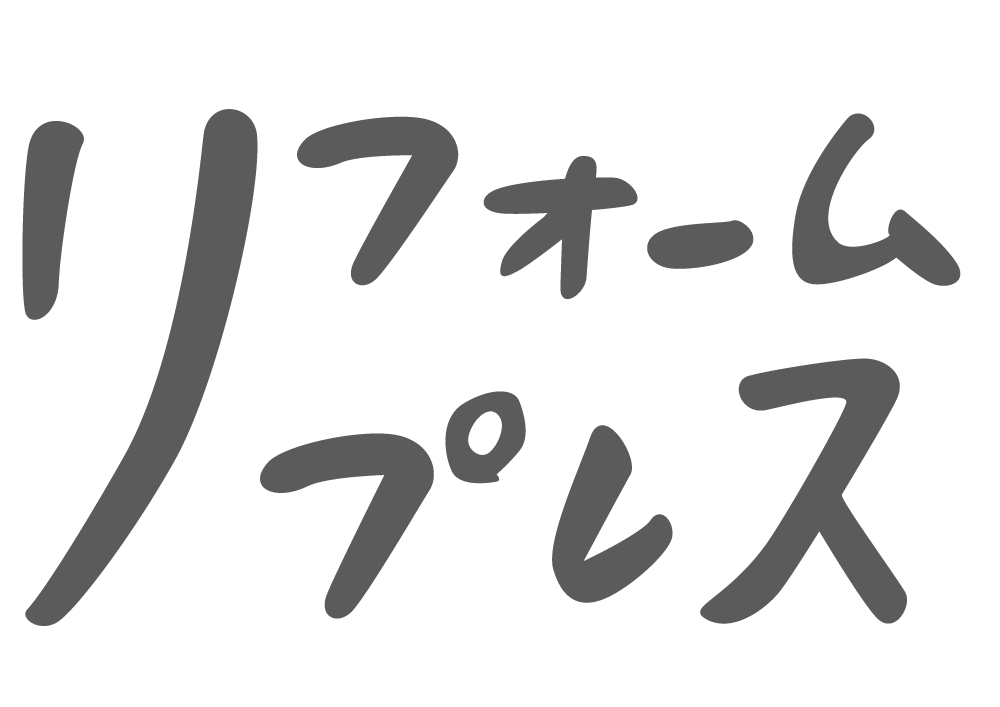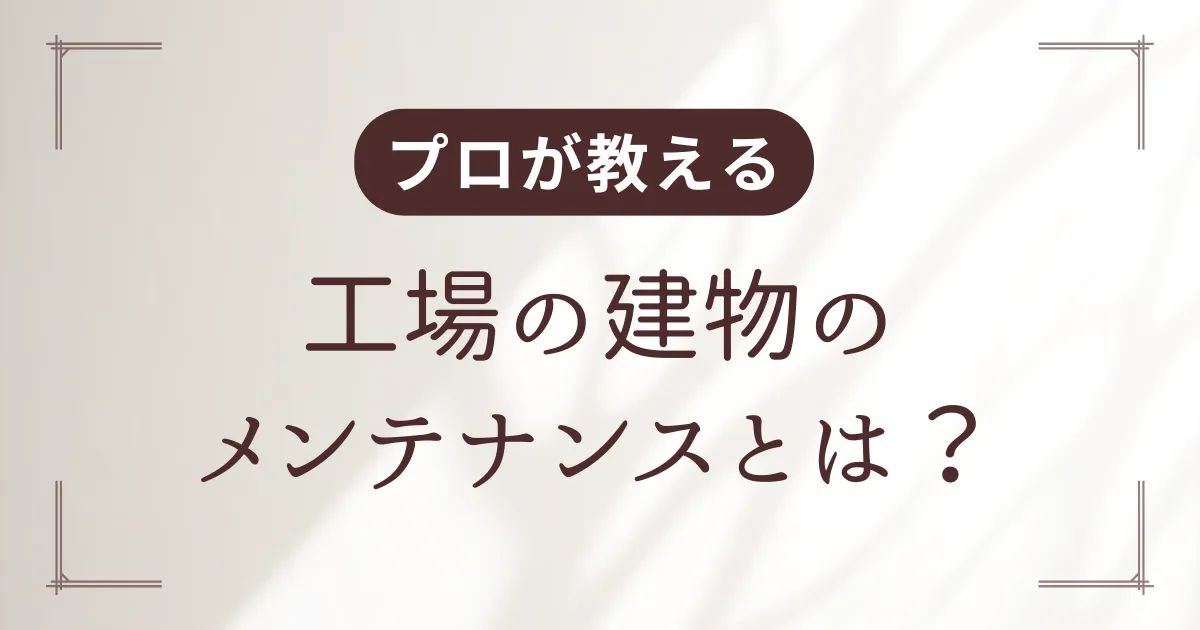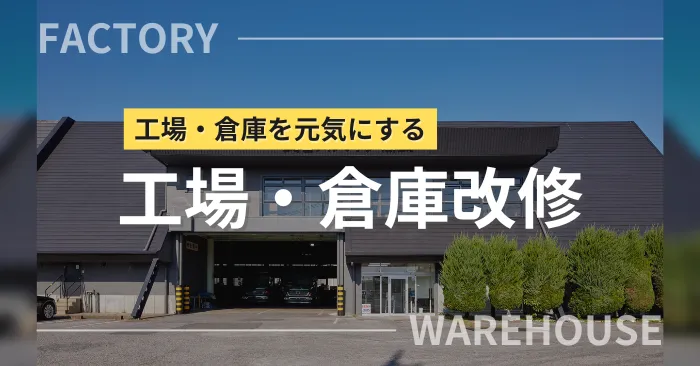工場の建物は、製造ラインや機械設備を支える「土台」として、企業の生産活動を根本から支える重要な存在です。
しかし長年の使用により劣化が進むと、雨漏りやひび割れ、空調不良など、さまざまなトラブルが発生するリスクが高まります。
また「外壁が劣化して見た目が悪くなってきた」「最近、空調の効きが悪い気がする」「床の沈み込みが気になる」と感じながらも、対処ができていない工場も少なくありません。
そこで本記事では、「工場の建物のメンテナンスとは具体的に何をするのか?」について徹底的に解説します。
目次
工場の建物のメンテナンスは具体的にどんなことをする?

工場の建物は、365日稼働し続ける生産現場の器とも言える存在です。
しかし年月とともに屋根や外壁、床、設備配管などは確実に劣化していきます。
そこで必要となるのが「建物メンテナンス」です。
ここでは代表的なメンテナンス項目について解説します。
1. 屋根・外壁の点検と補修
まず重要なのが屋根と外壁の確認です。
金属製の屋根はサビや塗膜の劣化、シーリング材の破断などが発生しやすく、放置すると雨漏りや構造部の腐食につながる恐れがあります。
外壁も同様にクラック(ひび割れ)や塗膜の剥がれなどがあれば、雨水や湿気が侵入し、内部の劣化を早めてしまいます。
点検では目視・打診・ドローンなどを活用して劣化状況を調査し、必要に応じて塗装の塗り替えやシーリングの打ち替え、防水シートの再施工などを行います。
2. 床・基礎の状態確認
床は人や機械が常に出入りする場所であり、劣化やひび割れが進むと安全面に関わります。
また基礎部分の沈下やクラックは、建物全体の安定性に影響を与えるため、定期的な点検が不可欠です。
床の補修にはコンクリートの補修、表面処理剤の塗布、防塵塗装などが含まれます。
基礎に関しては、必要に応じて地盤改良やアンカー補強といった大規模な対応の検討も必要になります。
3. 開口部(窓・シャッター・ドア)の点検
工場では搬出入や換気のために多くの開口部があります。
シャッターやスチールドアの故障、窓の破損・建て付け不良は、断熱性や防犯性に直結します。
特に台風や強風の被害を受けやすい部分でもあるため、可動状況のチェックや錆の除去、ガラスのひび割れ補修などが必要です。
4. 雨樋・排水設備の清掃と補修
屋根の雨水を適切に排出するための雨樋(あまどい)や、敷地内の排水溝も忘れてはいけません。
落ち葉やゴミの詰まり、傾きの不良により水が逆流すると、外壁や基礎を濡らして劣化を進めてしまいます。
定期的な清掃や破損部位の交換、排水勾配の調整などが必要です。
5. 屋上防水・止水工事
屋上は直射日光や風雨にさらされる最前線です。
防水層の経年劣化や破損は、内部への漏水に直結します。
防水シートやウレタン防水の点検・再施工を行うことで、長期的な漏水リスクを回避できます。
また雨水が溜まりやすい構造の屋根では、排水口の増設や屋根勾配の改善を行う「構造的な改修」も重要なメンテナンスの一環です。
6. 換気・空調設備の確認と更新
工場の稼働には適切な換気・空調が不可欠です。
特に夏場の熱気対策や冬場の結露防止、安全基準に準拠した換気量の確保は、作業環境の質を左右します。
古い換気扇や空調設備は省エネ性や冷暖房効率が劣るため、定期的な点検と更新計画が必要です。
最新機器への更新で、ランニングコスト削減にもつながります。
工場の建物はどのようにメンテナンスする?

工場の建物メンテナンスを効果的に行うには、問題が起きてから対応するのではなく、計画的・予防的に管理することが大切です。
ここでは工場の建物を維持・改善していくための基本的な進め方や考え方をご紹介します。
1. 定期点検を実施する
まず欠かせないのが年に1〜2回の定期点検です。
屋根や外壁、基礎、床、開口部、防水層、配管など、建物全体をチェックし、目視・打診・測定などを通じて劣化状況を把握します。
特に下記のような部位はトラブルが目に見えにくい一方で深刻な影響を及ぼすため、重点的な確認が必要です。
- 屋根材の浮き・サビ・漏水
- 外壁のクラックやチョーキング
- 雨樋や排水設備の詰まり
- 換気設備の動作不良
2. 劣化の程度に応じて段階的に対応する
点検の結果をもとに、対応の優先順位を決めましょう。
すぐに補修が必要な緊急性の高い不具合から、将来的なリスクを見越した予防的改修まで、段階的な対応がポイントです。
たとえば以下のように分類できます。
- 即時対応:雨漏り、シャッターの故障、外壁の剥離など
- 短期対応:劣化した塗膜の再塗装、屋上防水の再施工
- 中長期対応:断熱性能の向上、外壁材の全面張り替えなど
劣化を放置してしまうと後々の工事規模やコストが増大してしまうため、軽微なうちに対処することが、長期的なメンテナンスコスト削減にもつながります。
3. 日常管理と業務連携を強化する
建物の不具合や劣化サインは、実際に働く現場の従業員が最も早く気づくことが多いものです。
そのため日常的に異常を報告できる体制づくりも重要です。
たとえば
- 「最近、床の一部が沈むような感覚がある」
- 「強風のたびにシャッターがガタつく」
- 「空調の効きが悪く、暑さがこもる」
という小さな気づきを見逃さず、建物管理者と現場担当者がスムーズに連携できるような報告体制を整えておくことで、早期対応が可能になります。
工場の建物の寿命はどのくらい?

一般的に、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の工場建物の法定耐用年数は30〜50年程度とされています。
しかし、これはあくまで“目安に過ぎません。
実際の使用年数はメンテナンスの頻度や工場の使用状況、気候環境などによって大きく異なります。
たとえば定期的な塗装・防水メンテナンスが施されていれば、築40年を超えても良好な状態を維持している工場も少なくありません。
一方で、長期間ノーメンテナンスで放置されていた建物では、20年そこそこで雨漏りや構造劣化が深刻化するケースもあります。
また、建物の「寿命」は構造そのものの強度だけでなく、以下のような要素も影響します。
- 生産設備との整合性(レイアウト変更の限界)
- 断熱性・遮熱性などの快適性
- BCP(事業継続計画)対応
- 法改正による耐震基準への適合性
つまり、単に「何年使えるか」ではなく、「その建物が今の業務にフィットしているか」「将来の設備更新に対応できる構造か」といった視点も含めて寿命を判断する必要があります。
工場の改修工事は重要なメンテナンスの一つ

工場の建物が老朽化してきた際に求められるのは、単なる補修ではなく「改修」という視点です。
ここでは、工場メンテナンスにおける重要な改修工事の例を3つご紹介します。
屋根・外壁の全面塗装・張替え
屋根や外壁は紫外線や風雨、積雪など、過酷な環境に常にさらされています。
塗膜が劣化した状態を放置していると、下地の金属部分がサビたり、水分が浸入して断熱材や構造体を劣化させてしまうことに。
そこで行うのが遮熱塗料による塗装や、高耐久のサイディングやガルバリウム鋼板への張替えです。
美観が向上するだけでなく、室内温度の安定や雨漏りの防止、光熱費の削減など、機能面でも大きな効果を得られます。
また台風被害のリスクが高まる中、屋根の補強や耐風性能向上もセットで行う企業も増えています。
断熱性・遮熱性の向上リフォーム
建物全体の快適性と省エネ性を向上させるには、屋根裏や壁面への断熱材の追加、遮熱フィルムや断熱窓の導入といったリフォームが効果的です。
夏場の冷房効率が大幅に改善されるとともに、冬場の暖房効果も高まり、年間を通じて安定した温熱環境が実現できます。
特に働く人の安全性・快適性を重視する製造業では、従業員の体調管理や作業効率にも直結するため、重要な改修ポイントとなります。
老朽化した設備・開口部の交換
工場ではシャッターやドア、窓といった開口部の機能性が、日常業務の安全性や効率性に密接に関わっています。
経年劣化によって開閉が困難になったり、破損や隙間風が発生している場合は、早急な交換・補強が必要です。
また近年ではBCP(事業継続計画)の一環として、停電時でも開閉できる手動式シャッターへの変更や、断熱性の高いハイスペック窓への更新なども進んでいます。
建物の構造だけでなく、使いやすさや緊急時の対応力まで含めて見直すことが、現代の工場には求められています。
【まとめ】工場の建物のメンテナンスで改修工事が必要なら、お気軽にミサワリフォーム関東へご相談ください!

今回は「工場の建物におけるメンテナンスの基礎から具体的な対策、寿命や改修の考え方」までご紹介しました。
日常的な点検はもちろん、老朽化や使用環境の変化に応じた改修工事は、施設の安全性・快適性・生産性を守るうえで欠かせません。
ミサワリフォーム関東では豊富な実績と専門知識をもとに、現地調査からご提案、補助金活用まで一貫してサポートいたします。
「まずは相談だけでもしてみたい」という方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。